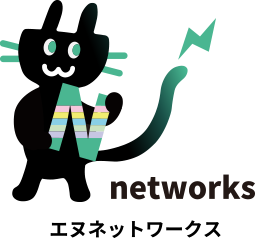電気工事の配管とは?施工別に見る工法と注意点を初心者向けに解説
2025/03/30
電気工事の配管についてご存じですか?
電気工事の配管は多様な種類が存在します。屋内と屋外、住宅と工場、さらに湿度や耐震性まで考えると、どんな配管工法が選ばれているのか分からず不安になるのは当然です。特にCD管やPF管、金属管といった専門用語が並ぶ中で、「失敗したら修正に数万円単位の費用がかかるかも…」という懸念もよく耳にします。
この記事では、家庭・店舗・工場といった利用環境ごとに最適な配管工法を解説。見た目の美観を保ちつつ、メンテナンスや安全性、そしてコストパフォーマンスにも配慮した「プロが現場で選ぶリアルな配管方法」を紹介します。
専門知識がなくても安心して選べるよう、分かりやすく解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。読了後には、あなたの配管選定の悩みがクリアになるはずです。
株式会社エヌネットワークスは、電気工事のプロフェッショナルとして、多様なニーズに対応するサービスを提供しております。特に、EV・PHEV充電設備の販売・施工に強みを持ち、ご家庭や事業所での快適な充電環境を実現します。その他、一般電気工事やコンセント増設、照明設置など幅広い対応が可能です。完全自社施工により、高品質かつ安心の価格でご提供いたします。電気工事のことなら、株式会社エヌネットワークスにお任せください。
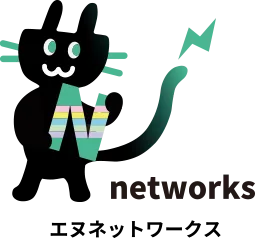
| 株式会社エヌネットワークス | |
|---|---|
| 住所 | 〒310-0912茨城県水戸市見川5-253-14 |
| 電話 | 090-2753-1445 |
目次
電気工事における「配管」の基本とは?初心者でもわかる電線管の役割と重要性
電気配管とは何か?どんな場所に使われているのか
電気配管とは、電線や通信ケーブルなどを物理的に保護し、安全かつ効率的に配線するための管のことを指します。建物内の見えない部分に電気を通す仕組みを整える重要な設備であり、火災や感電、ノイズなどのトラブルを防ぐ役割も果たしています。
電気配管は一般住宅だけでなく、工場、オフィスビル、病院、学校、商業施設、屋外照明設備、高速道路、地下施設など、非常に多岐にわたる場所で使われています。たとえば、屋外では防水性や耐候性が求められるためPF管が多く使われ、屋内の壁の中では軽くて施工しやすいCD管が選ばれることが一般的です。
電気配管の設置が必要になる主な場面には、以下のようなものがあります。
- 新築住宅や建物の電気設備工事
- リフォームや増改築に伴う電気系統の整理
- エアコン、照明、通信設備の増設
- 防犯カメラや監視システムの導入
- 電気自動車の充電設備の設置
- 工場や倉庫における電源ラインの強化
このように電気配管は、単に「電線を隠す」だけのものではありません。電気配線のルートを安全に計画・整理し、メンテナンスや増設のしやすさにも大きく関わるため、建築設計や設備工事の現場では極めて重要な工程となっています。
さらに、配線の種類によって適した配管材も異なります。例えば、高電圧ケーブルは強度の高い金属管で保護されることが多く、低圧や通信系ケーブルでは柔軟性のある樹脂管が使われます。
電気配管は用途や設置環境によって最適な管材を選び分けることが必要です。設置場所の湿度、温度、振動、紫外線などの条件を正しく把握し、それに応じた配管選定を行うことで、安全性と長寿命を実現することができます。
また、見えない部分の施工だからこそ、施工業者の選定や部材選びが大切になります。信頼できる電気工事士や施工管理技士が関わっているかどうかで、工事の品質は大きく変わります。電気配管は建物の心臓部とも言える存在であり、表には見えない部分にこそしっかりとした配慮が求められるのです。
電気配管の主な目的(保護、安全、美観、メンテナンス性)
電気配管の最大の目的は、電線を物理的に保護することです。電気が通るケーブルは非常に繊細で、外部の衝撃や湿気、温度変化、紫外線、害虫、化学薬品などによって劣化や断線が起こる可能性があります。配管で電線を覆うことで、これらの外的要因から守り、事故やトラブルのリスクを大幅に下げることができます。
次に、安全性の確保も重要な目的です。電気火災や感電事故の多くは、劣化した配線や露出した電線によって引き起こされます。電気配管を使うことで、万が一電線の被覆が剥がれても人や可燃物に直接触れることがなく、感電や火災を防止することが可能になります。
また、美観の観点も見逃せません。特にオフィスや住宅では、壁や天井に電線がむき出しになっていると、空間全体の印象を損ないます。配管を使えば電線をきれいに隠し、スッキリとした室内空間を維持できます。見た目だけでなく、配線のルートが明確になり、今後の増設や点検も容易になります。
さらに、メンテナンス性の向上も大きなメリットです。たとえば、将来的にLAN配線を増設したい場合、すでに配管が整備されていれば新しいケーブルを通すだけで対応できます。これにより、壁を壊したり、追加工事を最小限に抑えることができます。
電気配管の目的をまとめると、次の4つに集約されます。
- 電線の物理的保護(劣化・損傷から守る)
- 感電・火災などのリスク回避(安全性の確保)
- 室内空間の美観維持(見た目と整理)
- メンテナンスや増設への対応力強化(利便性向上)
特に近年では、スマートホーム機器やEV設備など、後から電気設備を追加する機会が増えています。初期段階で適切な配管計画を立てておくことで、将来の柔軟性とコスト削減にもつながります。
電気配管は一見地味な存在に思われがちですが、その役割は非常に多岐にわたります。住宅や商業施設、工場など、あらゆる建築物にとって欠かせない要素であり、電気設備全体の品質や安全性を左右する重要な基盤と言えるでしょう。
施工別で見る電気配管の流れと注意点(屋内、屋外、埋設工事の違い)
露出、隠ぺい、埋設配管それぞれの特徴とリスク
電気工事における配管方法は、主に露出配管、隠ぺい配管、埋設配管の三種類に分類されます。それぞれの工法には適した施工環境があり、誤った選定や施工は事故やトラブルの原因となります。ここでは、各工法の特徴、安全性、リスクについて詳しく解説します。
露出配管は、建物の内外に電線管を直接取り付け、配線が視認できるように施工する方法です。施工が比較的簡単で保守や増設も容易なため、工場や倉庫、一般住宅の後付け配線によく採用されます。使用される管は主にPF管や金属管で、強度が求められる場合には硬鋼電線管が使われます。一方で、見た目が損なわれやすく、外部衝撃や劣化にさらされやすい点がデメリットです。
隠ぺい配管は、壁や天井の内部に配管を通す方法で、美観に優れるのが大きな特長です。住宅やオフィスビルで主に用いられ、CD管やVE管といった柔軟性のある合成樹脂管が使われます。しかし、施工後のトラブル対応や改修が困難になるため、慎重なルート設計と正確な施工が求められます。また、熱や湿気がこもる環境では配管劣化が早まり、トラブルの原因にもなります。
埋設配管は、配管を地中に敷設する工法で、屋外の駐車場、庭、商業施設などの屋外電源供給に使われます。PF管や金属管(防食処理を施したもの)を使用することで、地中の圧力や腐食から配線を守ります。しかし、地中に埋めるため漏電や浸水のリスクが高く、地面の沈下や施工不良による断線事故が懸念されます。また、掘削や埋め戻し作業に手間がかかり、工期とコストの増加につながる点も考慮が必要です。
目的別・利用者別で変わるおすすめの配管工法
一般住宅向け:見た目/メンテナンス性を重視
家庭用の電気配管においては、安全性はもちろんのこと、住宅のデザイン性や快適性を損なわない配慮が求められます。特に新築やリフォーム時には、配管ルートの見え方、メンテナンス性、将来的な追加施工のしやすさなど、総合的な視点からの工法選定が重要です。
一般住宅における電気配線は主に屋内で完結するため、配線を隠蔽する「隠ぺい配管」が主流となります。天井裏や壁の中、床下などに配管を通すことで、居住空間に配管が露出することなく、すっきりとした内装を維持できます。一方で、施工後の修理や増設には一定の制約があるため、予備配管の確保や、将来的なアクセスを見据えたルート設計が欠かせません。
使用される配管材は主に「VE管」や「PF管」が中心です。VE管は合成樹脂製で耐熱性に優れ、屋内配線に最適です。PF管は可とう性に富み、曲げ加工が容易で複雑なルート設計にも対応できます。耐候性のあるPF管であれば、屋外の短距離部分や半屋外スペースにも使用可能です。
以下に、一般住宅でよく使用される電線管の特徴を整理します。
| 配管種別 | 特徴 | 使用箇所の例 |
| PF管 | 柔軟性・耐候性 | 床下・屋外対応 |
| CD管 | 施工性良好・低価格 | コンクリート埋設 |
共働き世帯や子育て家庭では、停電リスクや感電事故を防ぐための安全設計も重視されます。そのため、漏電遮断機との連携やブレーカーからの配線設計にも配慮が必要です。さらに、IoT機器やスマートホーム機能に対応した通信配線の追加ニーズも増えており、空配管(予備配管)の確保が現代住宅ではスタンダードになりつつあります。
また、照明やエアコンなどの配線が集中する場合は、モール配線を併用することもあります。特に後付け工事や部分的なリフォームでは、美観と利便性を両立させる選択が求められます。
このように、住宅用電気配管は単なる機能提供だけでなく、住環境の品質全体を左右する要素となります。施工前に十分な打ち合わせを行い、将来を見据えた計画的な配管設計が、安心で快適な暮らしの土台となるのです。
店舗・施設向け:安全性と拡張性を重視
店舗や施設における電気配管工法の選定は、住宅と比べてさらに高いレベルの安全性・可用性・拡張性が求められます。特に飲食店、美容室、クリニックなどの店舗では、火災リスクを最小限に抑えるための耐火性・耐熱性の高い配管材が選ばれます。また、施設の運営形態によっては、営業時間外にメンテナンスを済ませる必要があるため、施工性と保守性のバランスが重要になります。
店舗や施設での配管は、以下のような3つの基準を軸に工法が選ばれます。
- 高頻度使用に耐える強度
- 改装・増設に対応しやすい拡張性
- 来客を意識した美観と安全性の両立
特に電気容量が多くなる業態では、分電盤から各機器までの電線量が増えるため、太めの電線管が必要になることが多く、配線スペースの確保も課題となります。こうした環境では、金属管(ねじなし電線管・硬鋼電線管)が選ばれることも多く、火災時の耐熱性や強度面でも安心感があります。
また、配管ルートは多くの場合、天井裏や床下の隠ぺい配線が基本となりますが、メンテナンスを重視する施設では「ラック配線」や「モール施工」による露出工法をあえて選択するケースも見られます。特に飲食店の厨房など、湿気や油分が多い場所では、防湿処理や結露対策がされた専用管(PF管+防湿装置など)の採用も一般的です。
消防法や建築基準法に基づいた設備設計も必須となるため、管の種類や敷設方法、支持間隔などもJIS規格や各自治体の条例に準拠する必要があります。中でも防火区画の貫通部分は、耐火処理(モルタル充填や耐火スリーブ処理)を施し、火災時の延焼拡大を防ぐ対策が求められます。
また、商業施設では頻繁なテナントの入れ替えや設備変更も想定されるため、フレキシブルな設計が必要です。将来のために空配管を配置したり、天井内にケーブルラックをあらかじめ敷設しておくことで、配線の変更を容易にできます。
施設工事は一般的に法人が発注するため、見積書や施工要領書の提示、材料のJIS番号明記など、法的・契約的な整合性も求められます。こうした点からも、専門業者による設計・施工管理が非常に重要となります。
工場や倉庫向け:耐久性・高負荷対応が必要
工場や倉庫の電気配管工事においては、日常的に高負荷がかかる機器やシステムの安定稼働を支えるために、他の建築用途と比べて特に「耐久性」「安全性」「信頼性」が重視されます。加えて、大型機械や物流設備の存在、24時間稼働体制、重機の出入りなど、過酷な運用環境に耐える構造と施工精度が求められます。
このような現場では、配管材や工法の選定ミスが重大事故や生産停止につながることもあるため、電気工事の計画段階から入念な仕様設計が必要不可欠です。中でも、電線を通す管にはJIS規格に準拠した強度の高い「硬鋼電線管」や「ねじなし電線管」など、金属系の配管材が主に使用されます。
工場・倉庫用配管における重要な要件は以下の通りです。
- 物理的耐久性(重機や人の往来による衝撃)
- 湿気・熱・振動など環境要因への耐性
- 高負荷機器に対応するケーブル収容力
- 定期点検・更新時のアクセス性
たとえば、加工機械が多く並ぶラインエリアでは、高容量の動力ケーブルを複数本敷設する必要があり、配管サイズも通常より大きなものが使用されます。また、溶接作業や加熱装置がある場所では、火花や高温に強い被覆材と金属管の併用が一般的です。
また、倉庫では温度差や湿気による結露対策も必要です。特に地下や地中に配管する場合には「防湿装置」や「二重管構造」を用いたり、防水キャップで両端を完全に封じるなどの処理が行われます。加えて、配線の熱膨張・収縮によるたわみや破損を防ぐため、管支持金具の間隔にも細心の注意が払われます。支持間隔の目安が定められており、施工現場ではこれに準拠した設置が基本となります。
さらに、配管経路の選定においても作業動線を妨げず、かつ安全性の高いルートを取ることが重要です。高所配管では落下防止措置や支持補強が必須であり、地中配管では埋設深さの基準や打ち込み方式の選定にも専門知識が必要です。
生産効率に直結する配線設備だからこそ、設計から施工、定期点検に至るまで一貫して専門業者に依頼することが、トラブルを未然に防ぎ、長期的な設備の安定稼働に繋がるのです。
まとめ
電気工事における配管工法は、見た目やコストだけで選ぶと、思わぬ施工トラブルや後悔につながることがあります。特にCD管やPF管、VE管、金属管などの種類ごとに特性や使用シーンが異なるため、環境や用途に応じた的確な選定が不可欠です。
たとえば、住宅では配線の美観とメンテナンス性が求められ、配線モールやVE管のようなスッキリした見た目を実現できる素材が選ばれやすくなります。一方で工場や倉庫では、耐久性や高負荷への対応力が重要視され、硬鋼電線管や厚鋼管などの金属系配管が採用されるケースが多く見られます。
また、屋外や地下、湿気の多い環境での施工では、埋設深さの基準や防湿装置の取り付け義務など、JIS規格や電気設備技術基準に基づく高度な判断が求められます。施工ミスや安易なDIYによって、配線のショートや火災、漏電といったリスクを招く例も少なくありません。
配管選びを誤ると、放置したままでは数万円単位の追加費用が発生するだけでなく、建物の安全性そのものが損なわれるおそれもあります。だからこそ、用途や環境に合わせた配管選定を行い、専門業者による施工を検討することが、安心と効率につながる選択といえるでしょう。
株式会社エヌネットワークスは、電気工事のプロフェッショナルとして、多様なニーズに対応するサービスを提供しております。特に、EV・PHEV充電設備の販売・施工に強みを持ち、ご家庭や事業所での快適な充電環境を実現します。その他、一般電気工事やコンセント増設、照明設置など幅広い対応が可能です。完全自社施工により、高品質かつ安心の価格でご提供いたします。電気工事のことなら、株式会社エヌネットワークスにお任せください。
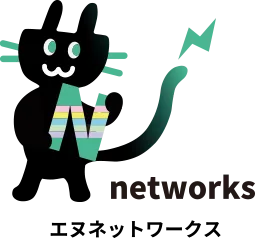
| 株式会社エヌネットワークス | |
|---|---|
| 住所 | 〒310-0912茨城県水戸市見川5-253-14 |
| 電話 | 090-2753-1445 |
よくある質問
Q. 電気工事における配管費用はどのくらいかかりますか?
A. 一般住宅の電気配管工事では、配管材料や施工方法によって費用が大きく異なります。例えばCD管やVE管を使った屋内の露出配管では、1メートルあたり約500円〜800円が相場ですが、PF管や金属管を用いた屋外や地中配線の場合は、施工が複雑になるため1メートルあたり1500円〜2500円程度になることがあります。さらに埋設配管では掘削や埋め戻しが必要になるため、1メートルあたり3000円以上になることも珍しくありません。使用する電線管の種類やサイズ、施工の難易度、配線の長さ、追加工事の有無によっても変動するため、事前に正確な見積もりを取ることが重要です。
Q. PF管とCD管では何が違い、どちらを選ぶべきですか?
A. PF管とCD管の最大の違いは耐候性と施工用途にあります。CD管は合成樹脂製で柔軟性があり、屋内の隠ぺい配管や配線モールとの接続に向いていますが、耐水性や耐候性が低く、屋外や湿度の高い環境には適していません。一方、PF管は屋外でも使用可能な防水・耐候仕様の電線管で、未来工業やパナソニックなどの主要メーカーから多数のラインアップがあり、屋外露出や埋設工事に適合しています。屋外施工や地中配線など湿気や紫外線の影響がある環境ではPF管の使用が推奨されており、JIS規格に適合した耐食性・耐久性の高い仕様で安心です。設置環境によって適切な種類を選定することが、安全かつ長寿命な配管につながります。
Q. 工場で使う電気配管に金属管を使う理由は何ですか?
A. 工場や倉庫では、高出力機器や大型の電気設備が多く稼働するため、電線管には高い耐久性と保護性能が求められます。金属管、特に硬鋼電線管やねじなし電線管は、高荷重や衝撃、火災リスクのある工業環境において配線や電線を確実に保護する役割を果たします。また、金属管は遮蔽性能が高いため、ノイズの影響を受けやすい通信ケーブルや制御線にも適しており、電磁波干渉への対策にも効果的です。さらにJIS規格に基づいた亜鉛めっき加工が施された製品は、耐食性・防錆性能にも優れており、屋内外問わず使用が可能です。施工コストは合成樹脂管より高くなりますが、安全性と長期的な信頼性を優先すべき現場では金属管の採用が主流です。
Q. DIYで電気工事の配管はできますか?違法にはなりませんか?
A. 一般的に電気配線を含む配管工事は「電気工事士法」に基づき、国家資格を有する電気工事士でなければ行えません。例えば、CD管やPF管の設置だけでなく、その内部にケーブルを通し、配線を接続する行為は「軽微な作業」の範囲を超えるため、資格なしで行うと法律違反となる恐れがあります。また、DIYでよく見られるトラブルとしては、絶縁不良、通線不良、防水不備などによる漏電や火災があり、修繕費や被害額が数十万円に及ぶケースも存在します。特に埋設や屋外配管では、施工基準を満たさないと建築基準法や電気設備技術基準違反となり、後から追加工事や撤去が必要になる可能性もあります。安全と法令遵守のためにも、電気配管工事は必ず専門の業者へ依頼することをおすすめします。
会社概要
会社名・・・株式会社エヌネットワークス
所在地・・・〒310-0912 茨城県水戸市見川5-253-14
電話番号・・・090-2753-1445
----------------------------------------------------------------------
株式会社エヌネットワークス
〒310-0912
茨城県水戸市見川5-253-14
電話番号 : 080-3355-2325
FAX番号 : 029-297-5353
----------------------------------------------------------------------